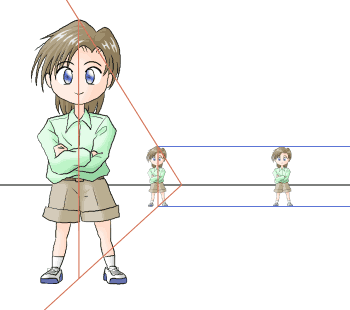
![]()
|
この図では、黒い線が地平線なのね。で、地平線上に適当な点を取って、パース線を引くわけ。あ、「パース」ってのはパースペクティブ…遠近法のことで、ここで言ってる「パース線」ってのは遠近を正しく取るための補助線のことね。 で、このパース線ではさまれた「高さ」は常に身長と同じになってるわけ。 さらに、このパース線の適当なところから地平線に平行な線を引くと、この高さも身長と一緒になってるんだ。こういうようなことを考えながら描くと、かなりそれっぽく描けると思うよ。 | |||
| ■ 貧乏人のためのCG講座 アラカルト編 |
絵を描く時に必ずついて回るのが、「遠近をどうやって表現するか」ということです。特に、背景に風景のようなものを持ってきた場合には、これができるとできないとでは、「らしさ」に大きく差がついてきます。
一番簡単なのはいわゆる「線遠近法」と呼ばれるものです…というと難しそうに聞こえますが、要するに「遠くのものほど小さく、平行線は一点に収束していくように見える」というアレです。
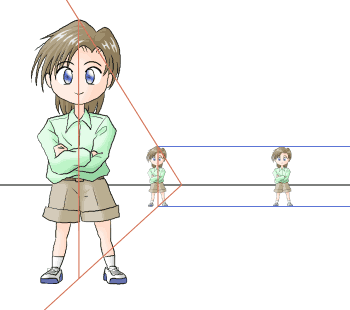
|
|
奥行きが短い絵ではこれだけでも用が足りますが、もっと広い空間を表現したい場合、もう1つの表現方法「空気遠近法」が威力を発揮します。
普段の生活でも経験することですが、うんと遠くにあるものは空気の中の微粒子などによって輪郭がぼやけ、固有の色が失われて青みがかっていきます。空気中の水分が多い時などはもっと手前でその効果が現れてきます。こうした現象を絵の上で再現するのが空気遠近法です。
 |  |
上の絵は、左が空気遠近法なし、右が空気遠近法ありのものですが、どちらのほうが奥行きが感じられるでしょうか・・・って、聞くまでもないですね(^^;。その効果は一目瞭然です。
・・・と、まぁ、この2つが美術の教科書にも載っている代表的な遠近法なのですが、実はまったく違う観点から遠近を表現する方法があって、CGを描く上ではこれがなかなか便利で強力なのです。
それは「カメラの性質を真似する」方法です。一眼レフをいじったことのある人なら実感できると思いますが、カメラで風景を撮影するとき、ピントは至近距離から無限遠までのすべての位置で合うわけではありません。どこかにピントを合わせれば、必ずそれより遠いところや近いところはピントが合わずにぼやけます。
そこで、例えば前景の人物を描きたいとき、下の絵のように背景を思いきってぼかしてしまうのです。この方法は前景と背景をつなぐ「中景」がない絵の場合、特に有効です。また、背景がどうせぼやけてしまうので、細かい描きこみをしなくて済む、前景が背景に埋もれにくくなるといった利点もあります。
 ここに出した絵だと小さくて分かりにくいかもしれませんが、ここでは背景となっている砂浜、海、パラソルなどをぼかしています。また、そのぼかし具合は遠くになるほど大きくなるようにしています。ただ、あまりやりすぎると何が描いてあるのか分からなくなってしまうので、ぼかすのはホドホドの強さにしておきましょう(^^;
ここに出した絵だと小さくて分かりにくいかもしれませんが、ここでは背景となっている砂浜、海、パラソルなどをぼかしています。また、そのぼかし具合は遠くになるほど大きくなるようにしています。ただ、あまりやりすぎると何が描いてあるのか分からなくなってしまうので、ぼかすのはホドホドの強さにしておきましょう(^^;